事例を読んで、A市社会福祉協議会の地区担当のB職員(社会福祉士)の今後の対応として、適切なものを2つ選びなさい。

くまみ
回答は2つ選んでね
〔事例〕
Cさん(20歳、知的障害)は、特別支援学校を卒業後、市内にある知的障害者通所施設に通っているが、地域の活動にも参加したいと思っている。そこでCさんの両親は、社会福祉協議会が主催する地区の住民懇談会に参加した際に、息子が参加できるような地域活動はないかとBに相談をした。Bは、この地区では高齢化が進み、地域活動の担い手の減少によって継続が困難となっており、商店も人手不足による閉店が増えていると感じている。
- Cさんから得意なことや、やってみたいことを聞き、この地区の中で活用できる社会資源を探す。
- 地域住民に対して、知的障害者に対するサービスを立ち上げるように促す。
- Cさんに対して、施設通所を一時休ませて、地域活動に参加するよう助言する。
- Cさんに対して、商店の後継者となれるように経営の技術を学んでもらう。
- 地域活動や商店の状況を把握し、Cさんのような人々の力を生かせる活動を地域住民と考える。


くまみ
答えは①・⑤だよ
✅ 正解
1,Cさんから得意なことや、やってみたいことを聞き、この地区の中で活用できる社会資源を探す。
- 本人の意思や希望を尊重したの支援です。Cさんの強みや興味を把握することで、地域資源とのマッチングが可能になります。
5,地域活動や商店の状況を把握し、Cさんのような人々の力を生かせる活動を地域住民と考える。
- 地域住民との協働によって、共生社会の実現を目指すアプローチ。
❌ 不正解(選ばない理由)
2,地域住民に対して、知的障害者に対するサービスを立ち上げるように促す。
住民のニーズや理解を無視している可能性があります。
3,Cさんに対して、施設通所を一時休ませて、地域活動に参加するよう助言する。
本人の意思や生活リズムを無視した一方的な助言であり、支援者としての適切な関わりとは言えません。
4,Cさんに対して、商店の後継者となれるように経営の技術を学んでもらう。
現実的な支援とは言えず、Cさんの希望や能力を確認せずに将来像を押し付ける形になっている。

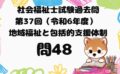

コメント